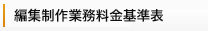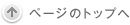『考える人』最終号を迎えて
河野です。座ってお話しさせていただきます。最終回のまとめに相応しいといまご紹介いただきましたが、そういう心積もりではなかったので、ちょっと困っております(笑)。
私は新潮社で『考える人』という雑誌の編集長をやっております。この雑誌をご存知の方は、挙手していただけるでしょうか。
そうですか、ありがとうございます。これくらいは知られていたということで安心しました(笑)。お買い求めになったことのある方は、もう1回手を挙げていただけるでしょうか。
これくらい売れているのであればよかったです(笑)。ありがとうございます。こういうことをお聞きしたのは、もうニュース等でご承知かと思うのですが、実は4月4日発売の『考える人』が最終号になります。雑誌の休刊が、突然1月半ばに決定しました。
この講座を引き受けたときにはこんな展開はゆめゆめ想像もしていませんでしたし、この編集教室のまとめに相応しいお話ができるのか、ちょっと悩んでしまいます(笑)。でも、状況が厳しいという話をすることは、決して悪いことではないと思いますし、私も別段打ちひしがれた敗戦気分でいるわけでもありません。
今週の火曜日で最終号の校了を終えたんですが、その前日、つまり3月20日の休みの日を使って、あらかた机の周りを整理しました。きれいにする前の写真と、片づけたあとの写真を並べて、「ビフォーアンドアフター」という形で今日ウェブにアップしました。
読者にはすでに休刊のお知らせをしていたんですが、その写真を見た人たちから、午後にはTwitter等で「休刊というのは本当なんですね」という反響が広がりました。
紙の雑誌の『考える人』は、昨年の4月に全体の頁数をスリム化して、価格を3割下げました。『Webでも考える人』というサイトを立ち上げ、さらにこういうトークイベントも積極的にやる、という3つを柱にしながらこの1年をやってきました。いろいろと手ごたえも感じておりました。
そこへ休刊という話なので、なんとも無念な話なのですが、今日はそのへんをありのままにお話したいと思います。
『婦人公論』大幅リニューアルの貴重な体験
ですから、前もってお断りするならば、「こうすりゃ儲かりまっせ」というような景気のいい話にはなりません。もともと私が目指してきたのも、そういうビジネスではなく、そこそこに儲かるし、食ってはいけます、面白い仕事をやればそれを楽しんでくれる読者がいます、というところを喜びにして、仕事をしてきました。
中央公論社でやっていた雑誌は『中央公論』という看板雑誌もありますが、私がむしろ楽しんだのは『婦人公論』という雑誌です。特に編集長として『婦人公論』をいまの大判にリニューアルしたときです。非常にリスキーだったんですが、いまだに生き延びている姿を見ると、あのとき思い切ってリニューアルしたのは良かったなと思います。
1998年3月7日のことなんですけれども、誰もうまくいくとは思っていなかったんです。いろんな偶然とスタッフの協力でうまくいきました。私の力というよりは、そういう「時の利」「天の力」の総和によって成功したと思います。
私自身は『婦人公論』のスタッフたちの仕事ぶりを見ながら、彼らがやっている仕事がもっとちゃんと人に届いてほしい(読めばそれを楽しんでくれる読者がいるはずだ)と考えていました。でもなかなかそれに読者がリーチ出来ていない。そこをどう突破するかが、リニューアルの焦点でした。
料理の味そのものを変える必要はなく、盛り付けであるとか、盛り付け以前に店構えがいかにもいかめしくて入りにくいのをどうフレンドリーな形にするか。それからメニューの組み方もいまの人がとっつきやすいようにちょっと変えたりする。そしてやはり自信を持って出せる老舗の味は自信を持って出し続け、それをなにもいま評判の味覚に合わせて変える必要は一切ない……等々。
流行り廃りに付き合っていたらきりがないし、流行っているものは必ず廃れます。頑固につくり続けたほうが生きながらえるということがあるので、やはりあまり目先に振り回されないで、なにを進めたらお客さんに喜んでもらえるかを見極め、自信を持って取り組んだほうがいい。私が『婦人公論』をリニューアルしたことと、いま我々がなにに取り組まなければいけないのかということは、基本的なところは全く変わりがないと思います。そのやり方とか知恵の出し方に違いはあるにせよ、本質は同じだと思っています。
『婦人公論』リニュ~ルの方法論を応用する
その『婦人公論』リニューアルの方法論を今度は『考える人』という雑誌に持ち込みながら、誌面刷新にトライしたのが1年前のことでした。
休刊のニュースが流れると、新聞でもすぐに取り上げられました。昨日も毎日新聞の取材を受けました。3月30日の同誌夕刊に載るはずです。その記者は、「こんなにいい雑誌がなぜ休刊になってしまうのか」、「この1年自分は面白かったという印象なのに、休刊理由がまったく分からない。どういうことだったんですか」と尋ねました。常連筆者の一人は、「『考える人』を休刊にして、新潮社は考えない人になるんだね」と笑っていました。書店主で電話をくださったある方は、「なんでやめるんですか。新しい読者が増えていますよ。毎号完売しています。もったいない」とおっしゃっていました。「村上春樹が売れているからって、それだけでいいわけはないでしょう」とまでおっしゃっていました。
新潮社には『週刊新潮』という大黒柱の雑誌があります。いまは『週刊文春』のほうが元気ですが、『週刊新潮』と、新潮文庫に代表される文芸作品が新潮社という会社の屋台骨でした。ところが、だんだんその柱がちょっとずつ細ってくる中で、『考える人』は15年前に創刊されます。
もう一つ別の路線の雑誌として、2002年7月に誕生しています。ですから、「もったいない」とおっしゃった人たちは、「せっかく新潮社さんとして15年間、新しい領域で新しい読者、新しい筆者の集う場をつくってこられたのに、それをなくすというのは、いかにももったいない、社としてその路線を否定したと外の人間は受け取りますよ」、という意見です。
実際『考える人』を舞台にしながら、いろんな筆者がいい仕事をしてくれました。たとえば養老孟司さんはほぼ毎号登場して、面白い仕事をしてくださっています。内田樹さんも連載など、いろんな形で関わってくださっています。
一番売れた号としては『村上春樹ロングインタビュー』というのがあります。これは村上さんを箱根のホテルにお連れして、2泊3日の徹底インタビューを行ったものです。
これは当時、電通がやっていた日本雑誌大賞の第1回受賞作になりました。
それから『小林秀雄 最後の日々』。小林秀雄の生前最後の対談の、生録音テープのCDを付けました。これは本邦初公開ということで、たまたま私が秘蔵していたものを、ご遺族の了解を得て付録として付けたのですが、NHKニュースがさっそく取り上げたりして、発売たちまち重版決定という号でした。
いろんな意味でヒット作も出しましたし、毎号そこそこに話題になった15年間なんですが、そうやっていろんな筆者がここを活躍の舞台にしてくれたり、話題になる号も出ていった、その『考える人』がなくなってしまうのは、正直残念でなりません。
『考える人』の2代目編集長に就任
私は、2010年6月に、この『考える人』の2代目編集長に就任します。前の編集長が退社するという話がその年の2月ごろに浮上して、そこで新潮社の方が、私に「ちょっと会いたい」と連絡してきます。
前の編集長は個人的にもよく知っていましたし、私が中央公論新社をやめたときに、「どうしてやめたんですか」と彼から聞かれたこともありました。今度は彼のほうがやめて、そのあとを私が引き継ぐのかと思って、非常に因縁めいたものをかんじなくもありませんでした。
そのとき、2代目編集長として最初にいったことは、「せっかく一定のファンがいてうまくいっている雑誌なので、自分としてはほとんど変えるつもりはない」ということでした。編集長が変わって雑誌のテイストを変えないというのは、逆に難しいことなんですね。
編集長が変わるとどうしてもカラーが変わります。ガラッと変えてうまくいく場合もありますし、逆に大惨敗するケースもあります。いろいろな例を見てきましたので、この場合はなにがいいかなと思ったときに、『考える人』という雑誌に関しては継続ということを心がけたいなと思いました。
ちょうど『村上春樹ロングインタビュー』が発売される直前でした。この雑誌の面白いところは、編集長がいて、あとはほとんど兼務のメンバーが、その都度のテーマに応じて、仕事を分担していくというやり方です。
そういう求心的なマインドと高いスキルを備えた編集スタッフがいるわけですから、彼らのモチベーションを大事にしなくてはなりません。編集長が変わったからといって編集方針まで変えるのは、無意味な混乱を生むだけであって、パワーがそこで落ちてしまいます。
個性の違いはいずれ出てきますから、変わるべくして変わっていって「ああ、違いが出てきたね」というのが、2代目編集長としての個性の発揮であって、もう腕まくりして「この雑誌を変えてやろう」と思う必要は一切ないだろうと考えました。
ただそういうスタンスを続けているうちに、やはり時間の経過とともにある種の型が雑誌を縛っているなということを感じ始めます。「考える人」はこういう雑誌だからというパターンが逆に縛りになってしまって、そこからはみ出していく力というのが生まれてこない。だから安定感はあるんだけど、固定ファンを中心にした、お決まりの味に満足しているような状態。ここは1回攻めに出なきゃいけないだろうなと感じ始めます。

その転機になって成功したのが、『小林秀雄 最後の日々』という号でした。編集部の人たちは、この特集テーマにあまり賛同はしてくれませんでした。慎重というか、方向性に対してもややネガティブな反応でした。
というのも、『考える人』というのは小林秀雄賞という賞の発表舞台なので、雑誌と切っても切り離せないのが、この小林秀雄という存在です。新潮社からは『小林秀雄全集』が出ていて、会社全体にとっても大きな宝です。ちょうど没後30年、生誕からは111年というタイミングでした。
没後30年。いまだに売れ続けている人ではありますが、いま小林秀雄を特集して、果たして売れるのかという懸念もありました。なかなか判断がつかないところです。
それから小林秀雄という人は、さっき申し上げたように、批評の神様のように言われる大巨人です。小林秀雄研究をしている人はいっぱいいます。有力な論者があまた控えている存在ですけれども、私はこの特集で、なるべくそうしたレギュラーメンバーを除外したいと思っていました。
小林秀雄賞の選考委員の人たちも今回はご遠慮願うようにして、さっきいった「雑誌の型を壊していく」冒険をそういうところから始められないだろうかと思ったんです。だからここは結構修羅場で、編集長である私が編集会議でそれを言ったときは、「非常にリスキーである」と発言した人もいました。
結果としては、一人の若い評論家に100枚の長い原稿を書いてデビューしてもらい、秘蔵のCDをおまけとしてつけたことなどで、この号は瞬く間に重版になって成功しました。
定価を3割下げる、雑誌を薄くする。
こうして私が編集長になってからの2番目のフェーズが始まったと思います。ただ、その間に消費税が上がったりとか、インターネットがますます普及するなど、雑誌がいよいよ厳しくなっていきます。雑誌不況が深刻化していきます。
『考える人』は季刊の雑誌で、発売当日に新聞広告が出るわけではなく、新潮社の出版広告に合わせて片隅にちょこっと小さく、お守りくらいの大きさの広告が出るくらい。そしていまは、新聞を取る人が減っている。だからその新聞を見ない人はいつ雑誌が出たか気づかない。どういう特集をやっているかも分からない。それからどんどん町の書店が減っている。雑誌を置いてもらえるところが減っている。
巨大書店メインの売場に行く雑誌ではないんですよね。どこに置くかといったら、たいてい文芸書と一緒に置かれるわけです。文芸ファン以外の読者の目にはなかなか触れない。さっき申し上げたように、読者とどういうふうにつなげていくか、誰に届けるかというところで目詰まりをしているという状況が、徐々に深刻化していくばかりです。
これをとにかくどうにか突破しないことには、『考える人』も先行きがない。編集部がいかに充実した号だと思っても、読者の知るところとならない、出たことも分からない、目に触れない、売っている場所がそもそも減っているぞ、という中でどう戦うか。
ではAmazonがそれに代わりうる存在になるか、ネット書店がそうなるかといったときに、これも完全に補うような場所にはなかなか育っていかない。『小林秀雄 最後の日々』は、NHKのニュースで取り上げられたので、ネット書店も在庫がすぐに底をついたりしましたが、よほど特別なことでもない限り、人がそこに殺到することは考えられない。
村上春樹と小林秀雄を毎号やれれば、それに越したことはないけれど、そうそういつもいいタイミングでいい材料がそろっているわけでもない。こちらとして訴えたいテーマはもっとほかにもあるわけです。
とにかく、編集部がこういう人に読んでもらいたいというところに、ちゃんと知らしめるような回路をつくるために何ができるかということを考える中で、去年の4月に15年目の新たなる一歩というのでリニューアルをやりました。
一番大きかったのは、1440円だったそれまでの定価を980円に下げたことです。3割以上安くしました。この時代、3割安くしたからって売れる雑誌になるはずがない、と、会社はそう判断していました。この点でも非常に孤立感が生まれました。
その分雑誌を薄くするということを行いました。300ページ近い厚さの雑誌だったんですが、誰に聞いても、やはり重い。買おうと思っても持ち帰る重さを考えると、「またにしよう」とつい置いてしまう。次に行ったときにはなかったり、買うのを忘れるという話をさんざん聞かされました。読む際にも、寝転んで読んでいると手がくたびれるので、なんとかして軽くしてくれないかということもさんざん聞いていました。「軽くしたいな」というのは作り手としても考えていたことです。
3分の2の厚さにしました。値段を安くする、制作費を絞る、原稿料をその分ちょっと抑えるという意味でも、薄くするというのはいろんな形でやったほうがいいということだったので、安くする、薄くするということをやりました。
じつは『考える人』の雑誌広告は創刊以来ずっとユニクロが単独スポンサーでした。そのユニクロの柳井社長の了解を早い段階でいただけたのは、リニューアルにとって大きな後押しでした。
ここまでお話してきませんでしたが、この『考える人』の編集理念、コンセプトは表紙に謳ってある通りです。「Plain Living & High Thinking」、これが編集方針なんです。昔はこれを「暮らしはつましく、思いは高く」というふうに訳していました。イギリスのロマン派の代表的な詩人、ワーズワースという人の詩の中に出てくる言葉です。それに対して、私たちは「Plain Living」を「シンプルな暮らし」、「High Thinking」を「自分の頭で考える力」というふうに訳しております。
創刊のときの編集長メッセージの一部を読ませていただきます。
「たまにはテレビを消して、身の周りも整理して、一人の私に戻り、自分の言葉と生活を取り戻したい。あふれるものや情報をいったんせき止めて、一息つきたい。思考する頭に新鮮な空気を送り込みたい。そんなあなたのために用意する静かな部屋に、季刊誌『考える人』はなりたいと考えています。」
これを創刊の言葉の締めくくりにしています。
私もこの考え方に賛同したので、この編集理念を引き継ぎながら、2代目の編集長をやってきました。ところが、この文章の冒頭にあります「たまにはテレビを消して」は、もう15年経ったいまや、「たまにはスマホの画面からいったん目を離し」なんですね。テレビじゃなくなったなと。
雑誌はコミュニティビジネスだ!
そういう大きな時代の変化の中で、何か変革しなければならない。そこに値下げとスリム化というアイデアも見えてきました。
同時に私が15年目の新たなる一歩ということでいったのは、私自身は雑誌をコミュニティビジネスだと位置づけています。読者と作り手が生み出す空間。雑誌という紙の媒体を間に挟んだ一つのコミュニティなんです。
言葉が生み出していく空間。そこには雑誌もある。イベントもある。
糸井重里さんの「ほぼ日刊イトイ新聞」に「一緒に何かやりませんか」とリニューアルの際にご相談しました。即「やりましょう。面白い」と応じて下さいました。4月4日発売の号なんですが、話を持って行ったのは3月の初めくらい。「4月の頭にイベントをやりたいんですけど」といったら、「やりましょう。面白いです」とおっしゃった。「ほぼ日刊イトイ新聞」のTOBICHIというところで、『考える人』の「おわりとはじまり展」というのをやってもらいました。
“おわり”というのは、いままで継続してきた流れが終わりになって、今度新しくリニューアルが“はじまり”ますよというものです。TOBICHIにいらした方がおありかどうか分かりませんが、一階部分と二階部分でできている狭い空間なんですけど、一階部分で「おわり」の展示をやって、二階で「はじまり」をやりました。
実はリニューアル号には養老孟司さんの「ヨーロッパ墓場めぐり」という連載の最終回が入っていたんです。その最終回の写真を「おわり展」で展示しました。TOBICHIというのは、窓を開ければそこに墓が見えるという、青山墓地の隣にある建物なんです。だからすごくピッタリで、ヨーロッパのお墓の写真が並んでいて、そこから窓の外を見たら青山墓地が広がっている。これは最高です。
その展示を一階でやって、二階ではリニューアル号の特集「12人の『考える人』たち」に登場してくれた12人の机を置いて、その人たちの言葉や写真を前にして、来た人が何かを書いて帰ってくださいというような展示にしました。たくさんの人がいっぱいそこに言葉を寄せてくれました。それを三日間やりました。
私がずっと店番をしていたんですが、一番驚いたのは、18歳くらいの女性が「TOBICHIがこういうことをやるというので来ました。『考える人』はもちろん知りません。私は雑誌を生まれてこのかた一冊も買ったことはないんです」と言ったんです。展示を見てその女性は『考える人』を買ってくれたんですが、その後『考える人』のファンになってくれたみたいです。
そういう、雑誌とまったく縁のない女性とそこで会うこともできましたし、いろんな人がTOBICHIの縁で、『考える人』の空間に入って来てくれました。そういうことなんです、コミュニティービジネスというのは。普通だとありえないような人たちが、そこに何かのきっかけで来て、いろんな刺激を受けてくれるような出会いが生まれる。そこに活路を見出していきたいというのが、私のリニューアルの考え方でした。
ウェブを立ち上げる! ワークショップを試みる
ウェブはいうまでもありません。ウェブでいろんな発信をしていく。もちろんTwitter、Facebookもやる。編集部でいまそれを担当しているのは一人です。究極のワンオペで、「すき家」以上だとブーブーいわれていますが(笑)、見事にこなしてくれています。
イベントのとっかかりは「ほぼ日刊イトイ新聞」と組んでやりましたが、その次は津田大介さん。彼のオフィスを使ってイベントを行いました。
女性カメラマンの安田菜津紀さんです。イラクに行ったり東北の被災地に行ったりして写真を撮っています。年をいっちゃいけないけど、今年の4月で30歳になる、本当に若い女性の写真家です。
いまラジオ番組を一つ持っていて、そのラジオも人気番組になっています。彼女に、外国で撮ってきたばかりの写真をスライドで映してもらいながら、イベントをやりました。津田さんのサイトも使いながら集客しました。
なので、これも『考える人』の既存の読者ではなくて、津田さんという集客力のある人のネットでの影響力を使ってやったら、全然違う人たちとそこで出会うことができました。それをきっかけに『考える人』の認知も広がったかなと思います。
それから『考える人』にはいま、4歳で視力を失ったエッセイストの三宮麻由子さんに、毎号エッセイを書いていただいています。私は三宮さんのエッセイを昔から愛読してきました。青山一丁目で目の見えない人が盲導犬とともに地下鉄のホームに転落して事故が起きたりとか、事件の性格も内容も違いますが、相模原の障害者施設で悲惨な殺害事件が起きたりする中で、やはり差別とか障害者の生きづらさということが話題になったときに、三宮さんに「ワークショップをやってください」ということをお願いして、会社の会議室を使って少し冒険的なイベントをやりました。
真っ暗にした中で、参加者にはアイマスクをかけてもらって、シーンレス体験と僕らはいったんですけど、かりそめの視覚不自由体験をやってもらいました。その状態で、「コンビニでお弁当を買ってみてください。パン屋さんでパンを買ってみてください」という模擬体験です。
実際にコンビニに行って弁当を選ぶ。これがいかに大変か。そしてそれがどういうふうに障害者のストレスになっているか。見えないと説明しても店員にはそのことがきちんと理解してもらえない。最近は外国人店員とのコミュニケーションの問題もありますが、たとえば自分のところでつっかえ、混雑する時間帯にお客さんが後ろに並ぶとか、「何をやっているんだ」という目線が背中に刺さるということもストレスになっているとか、そういうこともなかなか身をもって体験しないと、皆さんには分からない。
パンだって、あれは触わることができません。どういうパンの状態で、どういう味で、なにパンなんだということを食べるまで分からないで買えというわけですが、実際それに近いことが店先では行われています。僕らはまったくそれに気がつかない。何に困っているかも分からない。
駅で駅員さんが注意するだろうと思って見ていたというのが、青山一丁目のほとんどのお客さんの反応でしたが、駅員が本当にそんなことを全部できるかといったら、できるわけがないですよね。あの上り下りの電車をアナウンスしながら、他にもいろんなことをやっている。彼らは本当に神経の休まるところがないような中でやっている。そこに、目の見えない人が歩いてきた。「ああ、盲導犬を連れているから大丈夫かな」と思って安心した矢先にあの事故が起きているわけです。なんで落ちる寸前に誰かが声をかけなかったのかといったら、やはりみんな傍観しているだけなんですよね。あるいは、無関心。
そういうような事故は、三宮さんの目から見てどうなんですか。「僕らはなかなか声をかけられません。横断歩道で目の見えない人がいても声をかけられないけど、どうなんですか」というようなことを、そのワークショップを通じて、ざっくばらんに話してもらいました。
参加者はやはりその疑似視覚不自由体験に驚いて、「こういう体験をしてよかったと思った」というふうにいってくれました。でも、そういう体験をやったからといって、2万部の雑誌が2万5000部になっていくような、そういう成果は見えません。けれども、僕らはそういうことを積み重ねながら、一人でも多くの読者を増やしていきたいと考えていました。

「なぜ目の見えない体験を『考える人』がやるか」というのは、正にこれが考えることの根幹に関わるからです。それは想像力を持つということであって、自分の関心があることをネットで調べて、それに対する情報を得て生きていくということの繰り返しをやったり、スマホの中に縛られながら生きているわけですけど、そこから目を転じてよその世界になにが起きているかとか、いろんなことを考えていかないと、実は「盲目になっているのはあなたたちではないですか」ということに気付いてほしいというのが、僕らのメッセージです。
だから、考えるということの、気づきのワークショップとして、そういうこともやったりしている。これは本当に遅々たる歩みであって、それを積み重ねても飛躍的に部数が伸びていくことはありえないわけです。けれども、私はいまの時代にとって必要な出版の役割は、そういうことにもあると思っています。
毎週1回『考える人』のメールマガジンというのを編集長就任以来ずっと書いてきて、もう312回書いています。今日もアップされたのがあるんですが、そこから37本のメールマガジンの記事を集めて、『言葉はこうして生き残った』という本をミシマ社というところから最近出しました。
ミシマ社というのは小さい出版社です。この社を率いる三島邦弘さんとは彼が20代の頃にたまたま出会いました。彼はPHP研究所を皮切りに、NTT出版に行き、そして独立してミシマ社を立てました。「自由が丘のほがらかな出版社」っていったのかな。独立して一人編集、一人営業から初めて、いま社員が8~9人になって頑張っている出版社で、私も応援し続けています。去年のリニューアルを機に、彼が「このメールマガジンで本を一冊出しましょう」といってくれたんです。
そしてその次に会ったときに「こういうタイトルの本にできないかなと思う」といって、『言葉はこうして生き残った』というタイトルを彼が提示してくれたんです。
私はそれを見た瞬間、「そんな大それたことを自分は書いてきたつもりはない。こんな偉そうな本を出したらみんなから怒られちゃうよ」というような話をしたら、その次に会ったときには「こういう目次を考えました」というふうに彼が目次を持ってきてくれました。そうしたときに初めて「ああ、なるほど。これまで自分が書いてきたことは、こういう道筋になるものか」と思いました。
私は編集者として人の本は散々つくってきたんですけど、自分の本を人につくってもらったというのは初めてです。人が見て文脈を見出してくれるというのはこういうことなのかという逆体験が非常に新鮮でした。編集者というのはこういう役割をやってくれているんだなと、初めてそのありがたさが分かりました。
そんな経験もあって本を出して、これもいってみるとリニューアルをやったことがきっかけです。これは1月28日に出たんですけれども、リニューアル一周年を4月4日号でまた迎えて、この1年の成果をいろんな形で問いたいなと、編集部では話していました。
部数はその前の年に比べて3割くらい実売が増えました。定期購読も年間購読の料金が下がりましたので、一気に350人の新規受注が来たりして、こちらとしては予想外の手応えがありました。『考える人』の発行部数はずっと2万部の横ばいで来たんですけれども、800くらいまで落ち込んでいた定期購読の部数が、いま1300強に戻りました。
売価が3割安くなりましたが収支全体は変わってない。薄くして制作費の安くなった分をウェブのランニングコストに回していることで、収支を悪化させないで、でも部数は増えている。これをもって何が問題かというのが編集部の思いです。突然の休刊の決定に関しては残念というか不本意というか信じられないというか、これを評価しないで会社はなにを評価するのかというくらいに、編集部としては首をかしげました。そしてそれ以上に怒りました。そのよしあしをいうのは、今日は控えたいと思います。また、この結果が本当に見えてくるのは何十年か先だろうというふうに思いますので、それが正しかったか、間違いだったか、それはこれからの世の中と出版の関わりの中で決まっていくことだろうと思います。
ただ、負け惜しみではなく、この1年間やって来た方向性は間違っていなかったぞというのは、いまだに私が思い続けていることです。今日は本来であればその成果を皆さんに堂々と問いながら、これからの出版、ウェブと雑誌を両立させながら、こういうライブもどんどんやりましょうという呼びかけをしようと思ったら、休刊の話とセットになったという皮肉な顛末となりました(笑)。
紙とウェブとライブの3つのかけ合わせの実験
私のこれからの編集者人生は、そのことの仕上げに向かっていくフェーズだろうと思っています。『考える人』という雑誌がなくなるということで、私自身は3月いっぱいで新潮社は退社しようと思っております。なので、どこか次のステージでいまいったようなことを始めようと思っています。
なにも決まっていませんが、54歳に中央公論新社を辞めるときも、先のことをなにも決めないで、とりあえず「辞めよう」と思ってやめました。そこでネットメディアを立ち上げたいという若い連中に出会って、そこでウェブの会社に関わりました。辞めないという選択も非常に大事だし、いろんな事情で仕事を続けなければならない人たちも勇気のいることだし、辞めることが無条件にいいということではありません。しかし私自身は、自分がいってきたことと、人にそれを語り掛けてきたことのけじめをどこかでつけないといけないということがあります。また、これからも自分が自信を持っていい続けることのできる足場というものを、自分でつくっていくのが大事だろうと思っています。『考える人』という雑誌がない新潮社にいても、どういう形にせよ、自分が自信を持って腹の底から声を出して、はっきりと喋れなければなんの意味もないなというところで、雑誌の休刊を告げられたということと同時に退社するのは、自分の中ではなんの矛盾もなく決まったことです。
なので、本来ならば「まだまだ続くよ、『考える人』は」という中で、私も「リニューアル2年目をこういうふうにやっていきます」という夢を語りながら、この編集教室の最後の講座を話すはずだったんですが、ちょっと前提が変わりました。でも、紙とウェブとライブと、当面はこの三つの掛け合わせの中で、どういうふうに人の盛り上がりを演出していくかというところに、とにかくきっかけを求めていくということだろうと思います。
それを深刻に、「これしかないんだ」と思ってやっても、人は集まってきません。やはり楽しげにやっていれば、「なんか面白そうだな」と思ってくれるので、明るく楽しんで面白がってそれをやっていけたらなと思います。
さっきのシーンレス体験だって、三宮さんの話が面白いんです。彼女の話というのは、やはり耳の発達した人だから、日常生活の中ですごく面白い発見をいっぱいしているわけです。そんな話をしてくれながら、目の見えない人の五感の鋭さというので、「この人は目が見えないということがハンディかもしれないけど、別の才能、別の感性をこうやって広げているんだ」ということを、聞いて帰った人たちが感じています。
だから、活字とかなんとかもそうなので、必ずこの面白さに戻ってくる人が出てくると思います。現に周りにいる人で、Yahoo!をスマホのトップ画面から消したという大胆な人物がいます。「これがあるとついついどうでもいい、人の離婚の話なんかを朝に見てしまう。興味もないんだけど、あるとついそれをクリックしてずっと見ちゃう。そんな無駄な時間を自分から消し去りたいのでYahoo!を消した」という若い女性です。これも面白いなと思います。
いずれそういうことも含めて、ネットの情報とどうやって付き合っていくのか、どこからどこまでで線引きをして、自分の身を守るかということを、真剣に考えるタイミングが来ると思います。
ネット新聞『ハフィントンポスト』の創始者であるアリアナ・ハフィントンさんも、夜はデジタルデトックスの時間を設けると、自らいっています。そういうことから自分を遠ざけないと、この人生はクレイジーになると。ネット新聞を始めた人がいっているくらいですから、それはもう間違いない。必ずそういう反動の中に人間は行き始めると思うので、紙が絶望的だということもない。
ただ文明の利器として、ウェブというのは大いに利用していかないと、その紙の魅力に到達しない、体験しないままとおり過ぎていく人たちが増えていくこともあるので、そのウェブをうまく利用しながら、紙の魅力をどう体験してもらうかということだろうと思います。
そんなこんなの知恵を、皆さんが大いに発揮していただきながらやっていければ、決して真っ暗な話じゃないと思います。人の原稿を集めて紙の束をつくるのだけが編集の仕事じゃなくて、たとえばウェブをやっていくのであれば、ウェブにどういう面白い人がいて、どういう人と組み合わせてそれを編集したら、そのウェブの生かし方ができるのかということもあるだろうし、イベントでいえば、トークイベントだけじゃなくてワークショップとか、違った人でこういうことに関心がある人たちが集ったら、より面白い雑誌の発見のされ方をするんじゃないかとか、本の読者が広がるんじゃないかというつなぎ方もあると思います。
創意工夫をしながら、文字を、言葉を中心にしたコミュニティというのを目指していただければいいんじゃないかなというふうに思います。お時間のようですので、このへんで終わりたいと思います。
(平成29年3月23日(木)AJEC編集講座での講演より)