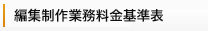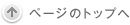現在は、女性誌「CREA」で副編集長をしていますが、7月までは同じ文藝春秋の社内でもまったくベクトルの異なる(笑)、総合週刊誌の「週刊文春」で特集班のデスクを務めていました。
話をさかのぼると、じつは今日の講演のお話は、2016年の正月に「週刊文春Woman」という臨時増刊を編集長として出して、おかげさまで完売となった頃にお声がけいただきました。恐ろしいイメージのある「週刊文春」のデスクに子育て中の女性が含まれていて、さらに“女性版週刊文春”という企画を実現させたというプロフィールを面白く思っていただいたようです。
その後、社内異動で畑違いの雑誌に移りましたので、今日はどんな立ち位置で話すべきか迷いつつではあるのですが……会社を起業されたり、すでに要職に就かれたり、という前回までの講演者の方々と比べて、若輩者の私が参考になる話ができるとしたら、社内異動のような話も含めた、「現場真っ只中のサラリーマン編集者が、会社の歯車になりながらもいかにやりたいことを通していくか」という実体験エピソードかなと思い、今日ここにおります。
私の場合、経歴を見ていただくと一目瞭然なんですが、ザ・サラリーマン編集者という感じで、入社以来17年間、社内異動を繰り返しています。就職の際には、全社員350人程度と大きすぎない会社規模で、上司を役職でなく「さんづけ」で呼ぶ社風などが気持ちよいなと思い、文藝春秋に入りました。もともと、週刊誌ならば「週刊文春」、スポーツ誌ならば「Number」、女性誌ならば「CREA」が好きで、人生の節目、節目に印象に残っている本にも文藝春秋のものが多かったんです。就職活動まではあまり版元なんて意識していなかったんですが、改めて読書歴を振り返ると「あ、この本もこの雑誌も文藝春秋だ。私は文藝春秋の出すものが好きなんだ」と認識したんですね。
で、入社してみてわかったんですが、文藝春秋には350人の社員の人事をあえてシャッフルし続けるという伝統があるんです(笑)。そのおかげで、異なるジャンルの雑誌、本にも、同じ文春マインドみたいなものが宿っているんでしょうね。私は350人の中でもシャッフル度が高いほうじゃないかと思います。新卒で入社して最初の2年間は「文藝春秋」という月刊のジャーナリズム誌にいて、3年目で「週刊文春」に異動しています。4年目で、これは自業自得なんですが、できちゃった婚をして約1年の産休・育休に入り、その後、5年目で職場復帰する際に女性誌の「CREA」へ。2年半経ち、女性誌の編集者として面白さを感じていた頃に「文藝春秋」に戻ることになり2年。ジャーナリズムの世界でやっていこうと覚悟を決めたら、今度は再び「CREA」に戻るようにいわれ、7年。この間に第2子を出産して、9カ月休んでいます。あまりに目まぐるしいので自分でも説明しながら訳がわからなくなるんですが、“入社以来最大の人生の岐路”といえば、やっぱり39歳のときの「週刊文春の特集班デスクをやるように」という異動辞令でした。数えてみると、12年ぶりの「週刊文春」復帰。早くに出産していたとはいえ、長男は小学6年、次男はまだ保育園児で5歳でした。「週刊文春」特集班では、休みはほぼ水曜のみ。土日は仕事でしたから、デスクをしていた2年間は、土日の夜に母親不在という家庭になってしまいました。
雑誌が売れない時代に、完売を続出させる編集体制とは?
前置きが長くなりましたが、言いたかったのは、今日は「『聞く』技術~取材対象から確実に本音を聞き出すには」という立派なお題をいただいているんですが、私はスクープを連発する「週刊文春」の“当事者”というより、たまたま居合わせた“目撃者”であるという心持ちなんです。でも、“目撃者”だからこそ気がついたこと、そして私みたいな異物も取り込めるところが近年の「週刊文春」の強さでもあるのかなというお話をしたいと思います。

今日、ちょうど2016年の流行語大賞候補が発表されました。「センテンススプリング」とか「ゲス不倫」とか、「週刊文春」から話題になった言葉がいくつもノミネートされていて、感慨深いです。最近、中学生くらいの子どもたちの会話に聞き耳を立てていたら、謎めいた話題になったときに「それはブンシュンに調べてもらわないと」なんて言葉をかわしていて、雑誌不況といわれる時代にもかかわらず、こんな若い子たちまでが「週刊文春」の名を知ってくれているんだと嬉しくなりました。
私は現在41歳ですが、20代半ばで「週刊文春」の下っ端記者をやっていた頃には、世間の人たちにとって週刊誌はもっと忌み嫌われ、新聞テレビより下に見られていたように思います。取材で聞き込みをしていると、「立派な大学を出ただろうに、なんでお前はこんな仕事をしているんだ」と怒鳴られたり軽蔑されたりして、自尊心がずたずたになっていましたね。
最近は、世の中の人の「週刊文春」を見る目がかなり変わったとはいえ、現場の記者たちが大変な苦労をしていることには変わりないと思います。「週刊文春」を面白いと思ってくださる人々が、だからと言って取材対象者として積極的に協力してくれるとはかぎりません。いま、マンションは大体オートロックですし、表札に名前を入れていないお宅もありますよね。ピンポンしているのが知らない人だったら、インターホンに応答さえしない人も多い。実際、私の自宅に「週刊文春です」と記者が訪ねてきたら、ドアを開けたくないなと思います(笑)。そんな時代に、記者たちが毎号、重要な証言を日本中でとってきてくれるということは、冷静に考えれば、奇跡の連続だなと思います。
「週刊文春」は木曜発売なんですが、木曜午前にみなさんが雑誌を手にとってくださる頃には、次の週の雑誌作りが始まっています。「週刊文春」には巻頭巻末のグラビアを作る8人程度のグラビア班、小説・エッセイなどの連載を担当する8人程度のセクション班、毎週のニュースを扱う40人程度の特集班があり、私は特集班の5人いるデスクの1人でした。特集班には5名のデスクのもと、それぞれ6~7名の記者が所属しています。
デスクの仕事は、木曜午前に自分の班の記者を集めて会議を行い、各5本のプランを聞き取るところから始まります。40人×各5本と考えると、すべての班を合計すると200本のプランが集まるということになります。その後、午後のデスク会議でこれはと思うプランを報告し合い、編集長を中心にどのプランに着手し、どの記者とどのデスクが担当するかを決めていきます。木曜夕方に各記者に発注したら、あとは月曜夜に記者が原稿を書くタイミングまで、日々取材状況をフォローし、取材の方向性を指示したり、場合によっては取材チームの記者の数を増やしたり、減らしたりしていく。怒涛の1週間の終わりは火曜日。火曜朝に記者が原稿を書き上げたら、即座に読んで、読みにくければ言葉を補って入稿し、その日のうちに校了までたどり着きます。
大雑把に説明してしまうと、特集班にはフリーランスの特派記者と社員記者がいて、若い記者は「アシ」、中堅になると「書き」となります。文字通り、「書き」は取材チームのリーダーであり記事の執筆者、「アシ」は「書き」の手足となって取材に駆けずりまわります。とはいえ、「週刊文春」では基本的にネタをとってきた人が「書き」となるので、若手でも「書き」となってベテラン記者を「アシ」につけることもあります。この切磋琢磨も、現場の活性化につながっているのではないかと思います。
週刊誌の仕事は、断られたところから始まる
「週刊文春」の記者と聞いて、どんなイメージを持たれるでしょうか。最近はエリート記者集団などと書いていただくことも多いようですが、文字どおり、多種多様なタレントの集まり。学歴も職歴もさまざまです。見るからに包容力があって、たちまち取材相手に信頼されるような人もいますし、パッと見は挙動不審だけれども野戦には強いみたいなタイプもいます。でも、共通するのは「人に相対したときに強さを発揮する」ということでしょうか。
先ほど若いときに取材先で怒鳴られて、自尊心がずたずたになったと言いましたが、結局、週刊誌の仕事は「断られたところから始まる」んですよね。記者たちからの報告を受けていても、「断られました」というのが非常に多い。でもその中で、誰ならば話してくれそうか、相手に迷惑をかけずに、あるいは相手にメリットをもたらすようにするにはどうしたらよいかと知恵を絞る。相手の立場も守らなければなりません。こうしたことを即座に機転を利かせて考えるアタマのよさが必要。直線的な思考の人は週刊誌記者には向かないかもしれません。
他社の週刊誌の方からもよく言われることなんですが、「週刊文春」の記者は本当によく働きます。アタマも働かせますし、足も働かせる。木曜夕方に発注した時点では五里霧中でも、早ければ土曜午前、遅くとも日曜、月曜午前には大体「奇跡」を起こしてくれます。
では、なぜ「奇跡」を起こせるのか。非常に単純な例だと、私の班に入社3年目で一見あどけない可愛らしい女の子なのに、高い確率で重要な証言をとってくる記者がいました。あるとき、タワーマンションに住んでいる有名人を訪ねていき、先方にとっては不愉快な質問をしたうえできちんとコメントも得ていたので、「よくタワーマンションでドアを開けてもらうところまでたどり着けたね」と尋ねたんです。すると、過去のインタビュー記事を調べたら虎屋の羊羹が大好物だとあったので、持参していたと。インターホンを押して取材の趣旨を伝えると、もちろん最初は取材を断られたけれど、インターホン越しに羊羹を見せて「これをお渡しだけさせてください」と頼んだらしいんです。で、ドアを開けてもらった瞬間を逃さず、質問を行ったというんですね。もちろん、そのときの質問の順序も見事だったのだと思います。こういう工夫の大切さって、週刊誌記者だけでなく、どの業界にも共通することかもしれませんね。
あと、他人に緊張感を抱かせないということも大事だったりします。でないと、ドアは開けてもらえませんから。私自身、こんな緊張感のない風貌なので、昔からナメられることが非常に多いんです(笑)。若いときはそれがコンプレックスだったんですが、だんだん、それでいいかなと。ナメていただいてこそ、相手の本性が見えますし、相手は無防備になってくれますから。そこで見えてくる人間らしさも、私は好きなんですね。腹が立つこともありますけど、「人間って、こういうものだよね」「こういう人だから、間違いを起こすんだなあ」と半ば愛情をもって見ている部分があります。
「こんなことを聞いたら……」は記者失格
週刊誌の記者が長いインタビュー時間をもらえることはほぼありません。ワンチャンスで聞くべきことをもらさずに聞かないといけない。だから、ピンポンを押す前や張り込み中は「これだけは必ず聞かないと原稿が成り立たない」という項目を頭に浮かべ、「相手はこんな反論をするだろう」あるいは「反論さえせずにドアを閉めようとするだろうから、そのときはこの質問をして興味をひこう」などとシミュレーションします。そしてドアを開けてもらえたら、相手の反応を見ながら丁々発止で質問していく。事前のシミュレーションはするけれども、そのシミュレーションには縛られないほうがいい。
そんな中、意外とできないのが、恥ずかしがらずにバカをやるということ。人ってどうしてもまともな人間のフリをしたくなりますよね。でも、週刊誌の記事というのは、綺麗事じゃない部分までくまなく取材してあるから面白いわけです。ならば、取材の際には「こんなことを聞いたらおかしいかな」「失礼かな」「聞くまでもないかな」などという躊躇は捨てないとならない。
今春、フジテレビの大型ニュース番組のキャスター就任が決まっていたショーン・Kという人物の経歴詐称を報じたときに、「書き」を担当したベテラン記者の取材で感心したことがありました。ショーン氏はハーバードビジネススクール卒など華麗な学歴を公式ホームページに掲載していたんですが、すべて嘘でした。取材を進めると、本名は川上伸一郎で、どうやら外国の血が入っているという触れ込みも怪しいとわかってきた。そこで、そのベテラン記者がショーン氏の実家を訪ねて、両親に会ったんです。すると、公式プロフィールには「父親はアイルランド人とアメリカ人のハーフ」とあるのに、お父さんはどう見ても熊本の普通のおじいちゃんなんです。名前も日本風。息子さんの経歴詐称について問うと、非常に戸惑っている。記者にも良心がありますから、ここで「これ以上聞いたら可哀相かな」「もう、日本人だとほぼわかってるわけだし」という躊躇はあるものです。でも、そのベテラン記者は、ドアを閉めようとするショーン氏の父親に「お父さん、お父さん、アメリカ人ですか? ハーフですか?」などと、ある意味、バカらしい質問をするんです。するとお父さんが九州弁で「なに言うとるかわからん」みたいな返答をする。出来上がった原稿で、このシーンはどんなもっともらしいことを書き連ねるよりも雄弁だったと思います。途中で引き返すことができなくなってしまった川上伸一郎氏の人生の悲哀を物語っていました。
記者には得意なことを担当してもらう

デスクになったとき、編集長から言われたことですが、「デスクの仕事でいちばん大切にしなくてはならないのは、それぞれの記者の得意不得意を見極めて、この人はこういう記事のときにすごく力を発揮する、逆にこういう記事のときはダメだった」と、それぞれが能力を発揮できる環境をつくるようにということでした。木曜のデスク会議でも、各記事の「書き」を誰にするか、その「アシ」を誰にするか、その「書き」と「アシ」が組んだときの化学変化はどうか、というところに「週刊文春」では非常に気を遣っています。
でも、だからと言って、一度決めたことにとらわれないのも「週刊文春」の強さかもしれません。朝礼暮改という言葉は否定的に使われることが多いですが、「週刊文春」ではむしろ雑誌の強みになっている。編集長自ら「俺の言うことは朝令暮改だから」とよく言っていたんですが、木曜夕方に各記者に取材を発注しておきながら、木曜夜のニュースや金曜朝のワイドショーのチェックなどを経て、金曜午前には別の取材に振り替えるということはよくあります。記者の側からすると「もうアポ入れしてしまったのに」「もう出張に来てしまったのに」など、思うところはあるはずなんです。でも、彼らは瞬時に切り替え、対応する。「わかりました。いま、世の中ではこちらのニュースのほうが大事ですよね」と理解できる記者が揃っているんですね。
私が「週刊文春」に行った2年前、2014年というのは、スクープを飛ばしているのになかなか完売が出ないという時代でした。業界では、週刊誌がスクープで売れる時代は終わったという考え方もありました。「週刊現代」や「週刊ポスト」に顕著ですが、スクープよりも、50代、60代以上の読者ターゲット層が興味を持っていそうなマネーや医療、性などの実用的な話題を大きく取り上げるようになっていました。ただ、そんな中でも「週刊文春」は「スクープこそがやはり週刊誌の醍醐味」だという姿勢を貫いてきた。2016年の完売というのは、突然変異ではなく、この2年間工夫してきたことが実ったのだろうと思います。スクープを売り上げにつなげられなかった過去の教訓から、ひとつのスクープを一過性のもので終わらせず、世の中の反応を見ながら、第2弾、第3弾と重ねていくうまさもあったと思います。
「直撃動画」が新鮮だった!
この2年間の工夫の中には、ネット上で2014年春からスタートしていた試みがちょうど実り始めたということもあります。それが「文春リークス」と「週刊文春デジタル」です。「文春リークス」は文字通り、文春版ウィキリークスです。週刊誌への情報提供は、従来は封書や電話がほとんどで、編集部のメールアドレスも公開していましたが、そんなに活況を呈してはいなかった。そこで、ネット上に情報提供サイトとして「文春リークス」を作って、24時間いつでも投稿を受けつけるかたちにしたわけです。投稿された情報は、複数の担当者のもとに自動転送される仕組みにして、編集部側も基本的には365日24時間体制でチェックしています。情報源を守るために具体的な記事名はあげられないのですが、これが非常にうまくいっていて、文春リークス発のスクープはたくさん生まれています。
一方、「週刊文春デジタル」は、ニコニコ動画でやっている有料チャンネルです。月額864円で最新号を含む直近の5冊分を読めるので、紙で買うよりもかなりお得になっています。「週刊文春デジタル」では、はじめは雑誌記事を転載しているだけだったのですが、途中から記者による取材直撃動画の公開を始めたところ、これが大変な人気を呼んでいます。
最初に大きな話題を集めたのが、育休議員こと宮崎謙介衆議院議員(当時)に不倫を問いただす直撃動画でした。これは民放各社のワイドショーから動画使用の依頼が殺到して、実際、全局で流されていたように記憶しています。
宮崎氏が妻の金子恵美議員の出産後に病院を後にして、路上でタクシーを待っている時に記者が問いかけるんですが、「不倫しているんじゃないですか?」と尋ねると、宮崎氏はバカにしたような笑みを浮かべるんです。質問を遮り、逃げようとする宮崎氏に、記者が「父親としてどうなんですか?」と迫っていくんですが、宮崎氏の人間性は一目瞭然なんですね。
同時に思ったのは、直撃動画では、取材対象だけでなく、記者の人間性も明らかになるのだということでした。じつは、「父親としてどうなのか」と問うている記者は、自分も妻が臨月の身で、そんなときに不倫をするとは何事かと、心から怒っていたんです。仕事でやっているのではなくて、本気で怒って聞いていた。それは、動画を見た読者にも伝わったと思うんです。
記者が撮ってきた直撃動画を見るたびに思っていたのは、「昔のワイドショーみたいで面白い」ということでした。私が子どもの頃は、梨本勝さんなどが芸能リポーターとして活躍されていた頃で、彼らには予定調和なしで取材対象に突っ込んでいく感じがあったんですよね。ブラウン管のこちら側の視聴者もドキドキした。でも最近は、記者会見でも事前に所属事務所から「これは聞かないでくださいね」と要請があったりして、レポーターたちが自粛している。視聴者もそれに気がついていますよね。
テレビのワイドショーで流れたときに思いましたが、「週刊文春」の記者が撮影した動画というのは、ブレてたりして、映像としてのクオリティーは低いんです。でも、その生っぽさがリアルで、印象に残るのだと思います。今は短い直撃動画が主となっていますが、ゆくゆくはマイケル・ムーアみたいな直撃ドキュメンタリーを撮る記者が出てきても面白いなと思います。
直撃動画で記者の姿が視覚化されたことで、“文春砲”への具体的イメージが人々の間に生まれつつあります。そのうち「この記者にだったら、私の持っているこの情報を提供したい」「この記者だったら、何とかしてくれるかも」と、動画で見た特定の記者を指名して、情報を提供する時代になっていくかもしれません。
週刊文春の女性版をつくったキッカケ
私が「週刊文春」特集班デスクになった2014年というのは、ちょうど「女性活用」という言葉が話題になっていた頃。異動の打診があったときは内心、「あぁ、ウチの会社における女性活用か」とツッコミを入れる自分もいました(笑)。
「週刊文春」はじつは、もう10年以上、女性読者の割合が4割を超えています。それこそ完売を出すためには、男性だけでなく女性にもウケないといけないんですね。各ニュースをどんな角度から取り上げるべきかを決める際に女性の感覚もほしいということで、以前から「特集班デスクに女性を」という声があったようです。でも、デスク適齢期の女性社員は子育て世代でもあるという難点があった。過去にいた女性デスクも、妊娠を機に異動していました。そんな中、私は出産が早かったのでそれなりに子どもが大きくなっていましたし、今の編集長とは過去に同部署にいたことがあって、顔見知りだったんですね。
私はこんなところでしゃべっておいてなんですが、人見知りで自信がない人間なんです。でも、好奇心だけは人一倍ある(笑)。だから、「自信はないけれど、望まれているのであればやってみよう」という思いと、「時代の変わり目なのだとしたら、そこに関わると面白いかもしれない」と思ってしまい、向こう見ずにも引き受けてしまいました。
いざ始めてみたら、本当に大変でした。他のデスクたちは皆、過去に「週刊文春」の「書き」として活躍したうえでデスクになっている。記者たちからの信頼があるんですね。一方、私は大昔に「アシ」を1年ちょっとやっただけ。「CREA」でデスクはやっていましたが、「あの女性誌から来た人、大丈夫なのかな」という視線は感じますよね。40歳を前にして、なぜ私はこの苦行を引き受けてしまったのか、と自分の決断を呪いましたね。編集長に言わせると、「今の週刊文春は同質的なメンバーで作っているから、あえて違う経歴の人間を入れたかったんだ。思ったことを遠慮なく言ってほしい」と。その期待に応えたいと思って精進しましたが、最初の1年は、敗北感にうちひしがれていましたね。その暗さたるや、家でひとり言が止まらなかったくらいです(笑)。
校了日の火曜夜に自宅に帰ると、よく皿洗いをしながら、「あの時、あの記者にこう指示すればよかった」とか、「校了時に編集長は『面白くなったな』とねぎらってくれたけど、絶対、納得してなかったはず」とか。反抗期真っ盛りの中学生の長男が「ブツブツ気持ちわりいんだよ」と文句を言うんです。でも、「抱え込んでいると病んでしまいそうだから、週刊文春にいる間は、家でぶつぶつ言い続けるから。私のことはあまり視界に入れないで」なんて宣言してましたね。
世の中では女性のリーダーをいかに増やすかばかり論じられているけれど、いわゆる会社のメインストリームである男の部署に活用されちゃった女性たちの大変さをすごく考えるようになっていきましたね。プラン会議でも「あの女性政治家、あの女性ビジネスマンがじつは無能でどうしようもありません」というネタってよくあるんです(笑)。私も編集者脳では、みんながそれを面白いと思うのはわかるんです。でも、きっとその女性たちはもともと「女性として」とか「女性だから」とか、ことさら意識したくなかった人なんじゃないかなと。けれど、役割として「女性代表」を担うようになり、周囲の好奇の目の対象になったんじゃないか。今、書店のデータを見ていると、「週刊文春」を購入する40代女性が非常に目立ってきているんですが、その中には“活用されちゃった世代の女性”が結構含まれるんじゃないかと思いました。
そんなときに、出版業界の改革の一環として、元日に発売するセブン—イレブン専用の雑誌のプラン募集が社内であったんです(福袋や新製品を正月に出す業種が多い一方、出版業界には長年、正月発売の新製品がなかった。そこで1月1日に雑誌を発売できる輸送ルートを持っているセブン—イレブンで元日発売の雑誌を出そうという試み)。「『週刊文春』好きの女性のために女性版週刊文春を出してはどうか」「女性誌でも週刊誌でもデスク経験がある自分にやらせてください」と、応募しました。40歳というと、会社人生も折り返し地点。異動が多かったので、編集者として専門性に欠けることがコンプレックスだったんですが、逆にいろいろ経験したからこそできるものがあるはずという直観もありました。
そうして発売にこぎつけた「週刊文春Woman」でジェーン・ス―さんが書いてくださったんですが、「(週刊文春は)私を『女』で括らない」と。多くの女性誌には「女は輝いてないと」という押しつけがましさがあるけれど、「週刊文春」にはそれがないから、女であることを意識せずにニュースを読める。だから、手に取る女性が増えているんだ、と。
その理屈でいうと、女性版を作る意味がないのではという話にもなるのですが、日々のデスク会議で二つ面白いネタがあってどっちをやるかというときには、やはり男性にウケるほうのネタが選ばれているんですね。落としてしまったけれど、本当は面白いのにと思っていたものがつねづねあって、女性版という形ならばやれるのではないかと思ったんです。一方で、通常の「週刊文春」との差別化をはかるために「Woman」とつけてはいるけれども、「女性による女性のための雑誌です!」という押しつけがましさはイヤだったので、男性が読んでくれてもいいなと思っていました。実際、普段の「週刊文春」の読者比が男性:女性が6:4とすると、「週刊文春Woman」は女性:男性が6:4。男性読者からの感想もたくさん届きました。
出産・子育ては仕事の障害ではない
「出産・子育ての両立をどうやっているか話してください」と言われていたのに、全然できてないですね。私の場合、都内の実家近くに住んでいまして、おかげさまで両親が元気なので手伝ってくれています。ここで両立のコツなんて偉そうに話したら、両親も息子たちも怒り狂うのではないかと思います(笑)。
ただ、「出産・子育てが仕事の障害なのか」ということに関しては、障害ではないですよ、と言いたい。私は第一子の出産がわりに早くて、入社4年目の最初に妊娠がわかり、4~5年目にかけて13カ月間、産休・育休で休んでいます。当時は保守的な会社で――今はそうではないことを声を大にして言いますね――、復帰前の面談で総務担当の男性に優しい笑顔で「デスクワークだけですむ、ラクな部署に回してあげますね」と言われたんです。

私は目が点になってしまって、それまで従順な社員だったのですが、「どういう意味ですか?」と質問しました。今、考えると、彼にしてみれば私は娘のような年齢でしたから、親心だったんだと思います。でも、当時の私は、「こんなにやる気があって働く気があるのに、なんて失礼」と。覚悟を決めて「お言葉ですが、私は週刊文春に復帰するつもりで、子どもを夜21時まで預かってくれる保育園を見つけました。実家の近くに引っ越しをして、親にサポートしてもらう体勢も整えました。今さらそんなことを言われても困ります」と述べたんです。一つ一つ部署の名前を示しながら「こちらはどうでしょう、こちらは」と聞いていって。最終的には「法律ではもとの部署に戻す、という決まりになっていると思うんですが」と言うと、「本人が納得すれば、いいんだよ」と言われました。もう、怒り心頭で「納得していません」と宣言して、帰りました。何度も言いますが、今はこんな会社じゃないです(笑)。その後、何とか入り込めたのが、今いる「CREA」編集部でした。当時は男性の編集長だったのですが、「結婚適齢期や新婚の女性が多い部署だから、周囲の理解もあるだろう」と拾ってくれたようでした。
では、出産・子育ては編集者にとって本当に障害なのか。たしかに回り道になる面はあります。でも、編集者の仕事の醍醐味とは、プライベートでの経験を活かせるということではないか、と思うんです。以前に「CREA」でよくやっていた「母になる」という特集があったんですが、それは産後まもなく就任した当時の女性編集長が「仕事をしながら、どう妊娠し、産み育てるか」という自身の経験をもとに考えたものでした。私も一編集部員として、自分の出産体験を踏まえて、企画をいろいろ作っていましたね。「週刊文春」でも、たとえば子どものいじめとか、夫婦の不和といった問題を取り上げるときには、プライベートでいろいろなことを経験しているからこそ、リアルに記事が作れる面があったと思います。
そもそもの話、私の場合、先ほども言いましたが人見知りで、今でも子どもと公園に行くと、他のお母さんたちと話すのに緊張してしまうくらいなんです。そんな素の自分の感覚と、編集者としての好奇心全開の感覚。どちらもあって、人としてバランスが取れているんじゃないかと思います。
(平成28年11月17日(木)AJEC編集講座での講演より)