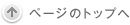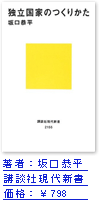 新刊『独立国家のつくりかた』(講談社現代新書)で、作家として国内の各メディアから注目される一方、海外ではパフォーマンスアートとして芸術活動を行う坂口恭平さん。しかも、彼から発せられる自身の肩書きは「建てない建築家」や「新政府初代内閣総理大臣」という奇想天外なものばかり。だが、彼の最新刊の中身は、意外にも実直に思考しつづけた一人の青年の“大人物語”であった。一体、彼は何を見て、何を感じて、何を考え、何をおこすのか。ご本人に直撃インタビューをした。
新刊『独立国家のつくりかた』(講談社現代新書)で、作家として国内の各メディアから注目される一方、海外ではパフォーマンスアートとして芸術活動を行う坂口恭平さん。しかも、彼から発せられる自身の肩書きは「建てない建築家」や「新政府初代内閣総理大臣」という奇想天外なものばかり。だが、彼の最新刊の中身は、意外にも実直に思考しつづけた一人の青年の“大人物語”であった。一体、彼は何を見て、何を感じて、何を考え、何をおこすのか。ご本人に直撃インタビューをした。

―― 坂口さんの日頃の発言や行動からは正直「ぶっ飛んだ」印象を受けるんですが、今度の新刊『独立国家のつくりかた』を拝読して、実は緻密な戦略を練って論理立てて思考していらっしゃる方なんだなという印象を受けました。ただ、「新政府誕生」だけが、坂口さんの全体戦略からは少し外れているといいますか、なんだか違和感を覚えたのですが、その点はいかがですか。
坂口:ご質問について段階的に説明していきますが、新政府は戦略ではないんですよ。いわゆる現代社会における固定された命題に対する戦略ではないんです。
まず、見ていただきたいのが、この本の1ページ目をめくっていただきますとわかりますが、《Practice for a Revolution》と記されています。つまり、この本に書かれている内容は、実は全部《Practice for a Revolution》を行っているということなんですね。
―― 確かにPractice for a Revolution、つまり、革命の練習とありますね。気がつきませんでした。その心は?
坂口:僕は、この社会がレボリューションを起こせないような環境でつくられていることに、どうやら幼少期から無意識的に気がついていたようなのです。それが起こせないっていうのを、それこそ六畳一間で兄弟三人が育っていく中で、なんとなく感じてしまって、俺自身の空間をつくるというのは、どうやらこの社会ではやりにくそうだなと感じていたのです。僕の場合、この社会で僕の空間が獲得できないのであれば、僕の中にある無意識的なものへと向かわざるを得ないと感じていました。「社会を変えようと思うんだけども、社会は変えられない」ということを早い段階で知ってしまったのです。それと同時に、「自分の中では変えられる」ということにも気づいたんです。つまり自分の中の無意識下にある空間を意識化することで僕自身の空間を見つけていきました。
―― 自分だけの妄想世界を作って、社会の見方を変えていったということでしょうか。
坂口:それって誰もが幼少期に経験してきた世界なんですよ。僕はそれを四次元世界だと言っていますが、子どもはその四次元世界を理解できるんです。たとえば、大好きな公園の向こう側が『エルマーのぼうけん』のジャングルにつながっていて、その先をいくと『オズの魔法使い』のイエローブリックロードにつながっていて、といった具合に。現実社会に自分の好きなものを自由につなぎ合わせることで、自分だけの都市空間をつくっていくのです。でもこの空間は、三次元世界で生きる僕らにとっては、なかなか言葉では説明できません。だから、みんなは成長するにつれて四次元世界のことは忘れてしまうんです。でも、僕は、忘れなかった。

―― 知覚的に今もなお、その感覚が残っているということなんですね。
坂口:僕は、知覚したすべてのものを脳内にある“感覚BOX”という箱の中にしまっています。しかも、その並び方はA、B、C、D……という順番ではなくて、感覚順にしまっています。そして、その箱が何個もたまっていくうちに、脳内には思考都市ができていきました。こうした感覚を僕は学校社会で知るんです。
たとえば、僕は学校社会で学級委員長をやっていたんですけども、委員長はいろんなことができるんだということを知ります。そして、子どもたちの先天的な才能、たとえば「足が速い」とか、そういう才能は学校社会を卒業したらあまり使えない、ということも知ります。また、違う小学校では僕らの学校社会とは異なる社会が存在しているということも知るんです。だから、学校社会はあっていいんですよ。僕は「なんで、学校社会を壊すんだ。学校社会だけは壊さないで」と言っているんです。なぜなら、学校社会で知り合ったあとの喜びがなくなってしまう。それは、どういうことかというと、同じクラスの女の子いますよね。学校社会という枠では気がつかなかったんだけれども、その後、その子は眼鏡を外すと「ものすごく可愛いかった」ということに気づいたりするじゃないですか。あの感じですよ。その経験こそが、僕にとっての喜び《It’s my pleasure》なんです。学校社会があったからこそ、僕は思考を始めました。「これではマズイな、これでは女の子にモテないな」と、最初はものすごく生理的なものからなんですけれども。
そこで、思考した結果、僕はマジックを覚えました。
―― マジックですか!?
坂口:そうなんです。僕は昔、マジシャンになりたかったんですよ。
(坂口さん、おもむろに十円玉を財布から取り出す)
坂口:ここに十円玉がありますよね。今、僕の手のひらに表側の十円玉が1枚あります。
(坂口さん、さっと十円玉を両手で隠してから開く)、裏ですよね。(再びさっと両手で隠して)さて、今、表か裏かどちらかわかりますか?
―― 裏、ですか?
(坂口さん、ゆっくり手のひらを開くと十円玉が消えている)
―― 消えました!
坂口:これは、ただのマジックですが、僕はこれでイリュージョンの根本を知ります。つまり、イリュージョン空間(四次元世界)と種明かしの空間(現実社会)の両方(これを僕はダブルバインドと呼んでいますが)の世界があることを知るんです。そしてそれだけではなく、そこにいた人たちとハッと息をのむ瞬間をわかち合えることも知りました。四次元世界では、人と人とはわかり合えないんですけれども“感情の共感”はできるんですね。
ですから、僕は、この“感情の共感”を徹底してやります。この“感情の共感”を言語化していくことは、またまた難しいことなのですが、僕は諦めないんです(笑)。母親から言わせれば、僕は「伝えたすぎで、諦めなさすぎ」らしいですけれども、この四次元世界があることで人は自由になり、そしてその自由は人に分け与えることができるという概念のみが、僕を突き動かしていくのです。だからこそ、人に伝わらないことがすごく悔しくて、悔しくて、僕は言語化を試みるのです。「どう、みんなこれ面白いでしょ?」「すごく面白いね」といったやりとりをしたくて。
ですから、僕は31年間、僕らが生きる現実社会で通用する言語化の練習を緻密に戦略立てて、思考し続けてきました。そして今、僕は、僕の感じている感覚すべてをテキスト化し、言語化できるところまでたどり着いたのです。

―― その成果物が御著書『独立国家のつくりかた』であり、海外でやっておられるパフォーマンス(芸術作品)なんですね。ちなみに言語化が成立し始めたと感じたのはいつ頃なんですか。
坂口:早稲田大学の建築学科に在籍していた頃、僕は路上生活者の方たちをフィールドワークしていたんですが、その後石山修武という大学の恩師が僕をディレクションし始めたんですね。ちょうどその頃です。
まず僕は多摩川河川敷に暮らす路上生活者の家(0円ハウス)を記録したレポートを出すんですけれども、先生に「多摩川だけじゃだめだ」と跳ね返されたんですよ。完璧なディスコミュニケーションが発生しました。そこで「これじゃダメだ、伝わらない」と隅田川に行って、見つけたものがソーラーパネルの家だった。その写真を一枚石山さんに見せると、先生はそばにいた研究員に「これ、コピーしろ」と回したんです。この「コピーしろ」という先生の手から研究員の手までの破線で描いた動線がもうしびれるんですよ。(先生は)この写真が芸術作品としてすごいってことが分かっているんですね。けれども、先生は、なぜすごいのかは説明しないんです。
―― 「コピーしろ」と指示する行為ひとつですべてを言い表していたんですね。
坂口:その行為、振るまい、それ自体が《educate=教育》なんです。教えることは《educate》ではないんですね。《educate》の語源を知っていますか? ラテン語のe-(外へ)とducere(導く)、つまり、《educate》は外へ拡張していくという行為を指すんです。これが、僕が初めて社会に向かっていった瞬間なのです。この《educate》が最高なのは、僕自身を導くのではなくて、僕自身が作った作品が、僕自身を社会に導いていく、ということなんです。これはたった一枚の写真なんですけれども、その作品が他者にも一発でわかるものだったからこそ、先生は「これ、コピーしろ」のひと言で僕を社会へと導いたのです。これこそが本来の経済であり、流通させるってことであり、交易なんです。その後もこうした先生とのやりとりを繰り返していくうちに、僕は、芸術が、経済が、僕と社会をつなぐ接点になることを知るわけです。そして、先生は僕にこう言います。「おまえは勉強するな、ただ今和次郎※1って奴をとりあえず調べろ、何も考えてなくていいから。おまえがやっていることは既に(彼が)やっている」というんです。僕はもちろん今和次郎なんて知りませんでした。今和次郎は、ご存知ですか?
―― いや、知りませんでした。どんな方なのでしょうか。
坂口:今和次郎は、画家であり、建築家であり、民俗学者でもあった人です。彼は、都市化していく東京の街の様子や人々の暮らしを採取していく現代風俗を提唱するんですけれども、当時の僕は知りません。ただ、その時先生に言われたのは「俺が言ったことを忘れるなよ」だったんです。だから僕もすぐに了解しました。もちろん、意味はわからなかったんですけれども、「俺の言ったこと忘れるなよ」と僕に言う人はほとんどいなかったんですよ。こうして石山修武は、僕にたった4年間という短い間に全部教えてくれたんです。経験のグラデーションを教えてくれました。だから、僕は「伝わらない」という絶望から救われ、徐々に心が満たされていくのです。
―― 石山修武さんの存在がものすごく大きかったのですね。
坂口:僕の師匠はみな大人であり、ジェントルマンでした。大人にもいろいろあって、貴族とか賢人とかあるんですけれども、路上生活者として僕が尊敬する多摩川のロビンソンクルーソー※2やビートたけしさんもそうでした。
あるテレビ番組でビートたけしさんを多摩川河川敷に住むロビンソンクルーソーのところに案内したことがあるんですけど、僕がたけしさんにメールで書いたのは「長靴で来てください」だったんですよ。すると、たけしさんは、ロールスロイスで多摩川に来ました(笑)。けれども、ちゃんと長靴を履いてくるんですね。つまり、たけしさんは気づいているんです。ロビンソンクルーソーのほうが光が強くあたる場所にいることを。本当のヒエラルキー序列を。これは、途轍もないことです。僕は、たけしさんにもちろん敬語でしたけれども、たけしさんも僕に敬語で話しかけてくるんですよ。そして、「全部、本を読みました」と言うんです。そして『ゼロから始める都市型狩猟採集生活』にしか書いてないことを三つくらい僕に伝えました。これも「コピーしてくれ」とおなじく、かなりデリケートな瞬間だったんです。そして、ロビンソンクルーソーの家にお邪魔したときも、彼はたけしさんに自分で作った柿を渡すんですね。そして、たけしさんは自分でその柿を切って食べる……という行為の連続が僕の目の前で繰り広げられるんです。「これってすごいな」と思いました。その時、僕はギリシャ哲学者のディオゲネスとアレキサンドロス大王との対話を思い出しました。それは「ちょっと日が当たらないので、アレキサンドロス(大王)さん、どいてください」※3という西洋的なディオゲネスさんよりも、俺はオシャレでジェントルマンな振舞だなと思ったんです。

―― こうした恩師たちとの出会いの中で坂口さんはご自身の足と嗅覚で“生きるための技術”を身につけてこられた。その経緯はこの本に書かれていますね。
現在は、ご自身が零塾などを立ち上げて《educate》をしていく立場だと思いますが、その《educate》する側とされる側の境目みたいなものはあったのでしょうか。
坂口:まず、コップに注ぐ水にたとえましょう。僕の子どもアオちゃんが携帯をいじっているとします。子どもにとって携帯はおもちゃですから、アオちゃんは面白くて、面白くて夢中で携帯をいじっています。この状態を俺の脳内では、空のコップの中に水が注がれていく映像に変換されます。この水は、アオちゃんの欲望が満たされていくにしたがって、どんどんコップの中に溜まっていきます。これを僕は自己実現と呼んでいます。アオちゃんは携帯をいじっています。コップの水位は高くなっていきます。アオちゃんは、いじっています。どんどん水は溜まります。そこにアオちゃんの友だちが「携帯を貸してほしい」と言います。けれどもアオちゃんは貸したくありません。そこで、僕の奥さんが空気を読んで「アオちゃん、あとで返すから、ちょっとだけ貸してあげて」と携帯を取り上げて友だちに渡します。けれどもアオちゃんに“あと”という概念はありません。子どもには“いま”という概念しかありません。
だけど、空気を読むとそのことを忘れてしまうんですよ。すると、“いま”を取り上げられたアオちゃんのコップの水は一気になくなり、空っぽになってしまいます。欲望は満たされません。 そこで、僕はもう一度、その子から携帯を取り戻してアオに返します。またアオちゃんは携帯に夢中になります。ある程度、その子に見せつけながら。水位はグングン上がっていきます。アオちゃんは、まだいじっています。水は溜まります。すると、今度はアオちゃんのお隣りで談笑が始まります。アオちゃんの耳にも楽しそうな声が聴こえていきます。アオちゃんはまだ携帯をいじっています。僕の脳内映像では、コップの水があふれ、床にこぼれ落ちています。そこで、僕が動きます。僕は、あふれた水の受け止めるために別のコップを手にします。そして、そのコップであふれた水を受け止めます。このあふれた水を受けとめる行為を、僕は、社会実現と呼んでいます。そして、これを“親子”といいます。つまり、自己実現と社会実現は同時に行っていかなければならない。人と人が協力しないと、大人になれません。そして、心が満たされなければ、社会に向かえないんです。
そこで、僕はもう一度、その子から携帯を取り戻してアオに返します。またアオちゃんは携帯に夢中になります。ある程度、その子に見せつけながら。水位はグングン上がっていきます。アオちゃんは、まだいじっています。水は溜まります。すると、今度はアオちゃんのお隣りで談笑が始まります。アオちゃんの耳にも楽しそうな声が聴こえていきます。アオちゃんはまだ携帯をいじっています。僕の脳内映像では、コップの水があふれ、床にこぼれ落ちています。そこで、僕が動きます。僕は、あふれた水の受け止めるために別のコップを手にします。そして、そのコップであふれた水を受け止めます。このあふれた水を受けとめる行為を、僕は、社会実現と呼んでいます。そして、これを“親子”といいます。つまり、自己実現と社会実現は同時に行っていかなければならない。人と人が協力しないと、大人になれません。そして、心が満たされなければ、社会に向かえないんです。
―― それが個人の自立と解釈してもよいでしょうか。
坂口:はい、人は心が満たされないと「それは満たされないものなんだ」と認識してしまいます。すると、人は自立できない。ただ、上手な人は満たされていないんだけれども、「お前のことが好きだ」と抱きしめられることできちんとそれを閉じ込めることもできるんです。僕はいま心が満たされているんです。さきほどのご質問の、僕自身が社会実現に変わった瞬間についてですが、実は3.11を境に僕は変わりました。それを僕の脳内イメージでは、さなぎが蝶にメタモルフォーゼ(変態)する感覚で変わりました。ちなみに、さなぎの中身ってどうなっているか知っていますか?
―― さなぎの中身ですか?……芋虫と蝶の中間みたいな物体が縮こまっているんでしょうか。
坂口:実は液体なんです。ここからは、話がぶっ飛ぶかもしれませんがいいですか?(笑)
その液体って僕からすると“直感の象徴”って感じがするわけですね。液体って固体の次元がすべて削ぎ落ちていて影みたいになっていくんです。四次元世界の事象が色濃く投影するのではなくて、ちょっと貫通しているみたいな濃淡あふれる《shadow=影》です。影の話をすると長くなるので省きますが、だから僕は芋虫の段階までは、自分で生きるために徹底的に戦略を練って、論理化して言語化していく作業をしていました。それで、芋虫からさなぎになった瞬間は、2010年10月18日のことでした。そのとき、僕は生まれて初めて、直感を使います。そこで初めて生まれたのが、零《zero》という概念をなんですよ。それまで僕は、直感は使えませんでしたが、今はもう何も怖くない。自分の直観を信じられる。だから、今はもうすべて後付けでやっています。新政府樹立も後付けです。僕はもう直感だけで生きている直感人間なんですよ(笑)。そこからほとんど啓示に近いような概念が生まれてきた。すべてアンロジックなことだけをやり始めた。直感って僕がこれまでの31年間くらいかけてやってきた言語化の土場がないと使えないんですよね。今、振り返ってみると、さなぎから蝶になるまでは恐ろしく早くて、10月ぐらいからずっとグラグラっときていたんですけれど、2010年11月、12月、1、2、3で一気に押し上げられて外に出てったんです。さなぎから蝶になりました。もう3.11で完全に《educate》したんですよ。

―― なるほど、3.11を境に蝶になられて、社会実現として新政府を誕生させたということですね。少しまとめますと、この本にある芸術と経済の役割である「生きるための技術を教える行為」というのは、自己実現と社会実現の双方を満たしていく行為だということがよく理解できましたが、この本にはもう一つ「共同体のあり方を考える行為」も記述されていますよね。こちらはどのように捉えているのでしょうか。
坂口:僕は、この現実社会の中で問題があるようには思えない部分が一つだけあります。それが、僕が感じている“共同体”です。つまり、まさにこの喫茶店の空間です。僕がここでインタビューを受けていて、隣の席にまったく知らない人たちが談笑していて、その向こう側にクリエーターの方が座っています。僕はさっき彼を見つけて挨拶しにいきましたけど、僕は彼に会ったことないんですよ。
―― えっ!? 会ったことはなかったのですか?
お知り合いかと思いました。
坂口:僕は彼といつか出会えるとわかっていたので、事前にネットで調べて彼の顔を覚えていたんです。こうした空間を僕は、完璧な共同体と見なしています。だから、僕は、人と人が出入りする空間が好きだし、人と人が交易できる空間が好きなんですね。こうした空間に足を踏み入れたときの「なんかあるよね」という感覚は、“あの街”というのが、実はもう既にこの世に存在しているということをちょっとだけ感じさせる、あの瞬間なんですよ。現実社会から“あの街”につながっていく、あの頃の感覚なんです。それを、ある誰かさんは、喫茶店でタバコを一服してわかっちゃうひともいれば、ある誰かさんは、マドレーヌと紅茶でわかっちゃったりするような認識の連続がある(笑)。
―― なるほど、坂口さんにとって共同体とはすでにこの社会に存在しているものであり、最近、流行しているコミュニティ論とはまた異なるニュアンスのような気がしました。けれども、そのあたり誤解されることも多いんじゃないでしょうか?
坂口:僕は、共同体を認識でやっているんですよ。僕は、共同体を造るつもりはありません。この空間の「なんかあるよね」や「しびれるよね」という“感情の共感”をただやるだけです。それを人は忘れないんですよ。すべては人と人との出会い、つまり “縁”なんです。ここからまた話がぶっ飛びますが、この “縁”を僕の抽象概念で投影すると、涙の《tears》になります。またまた液体がでてきちゃうわけですよ。しかも、《tear》(涙の単数形)ではなくて、二人の涙が合わさってできる《tears》(涙の複数形)なんです。それは、目と目が合って、実は目は空洞なんだということがわかっちゃうような、貫通するような、だからこそ、僕らのいる現実社会に投影すると、液体になっちゃうような、そんな感覚です。僕は、今それを三人同時にできるんじゃないかと試しているんです。それは説明できません。説明できたら、たぶん四次元世界じゃないですし。だから、《tears》を可能にするためには、説明じゃないんですよ。そこで、僕は音楽化しているんです。でも、そんなこと言ったってわかんないじゃないですか(笑)。だから、技術を磨いて僕が変化していくのを「見とけよ」というのをやっているんです。
それこそ、この本だって、初めはすべて言語化できていませんでした。実際、2008年に一度、この本の編集者である川治君に一ヵ月で350枚の原稿を書いて渡しているんですよ。でも「まだ(出版する)タイミングじゃないな」と判断して、僕が止めたんです。なにせ、その頃、僕はさなぎにもなっていませんでしたから(笑)。それと同じことで、僕はいつも可能性の手前の可能性を見ています。現に嬉しいことに、この本を読んだ読者からたくさんの反響をいただいています。年配の方から14歳の子まで。さらにちょっというと、僕の中では14歳も年配の方もみんな同い歳なんですよ(笑)。
―― え!?
同い歳といいますと?
坂口:中国の絵巻で0歳、1歳、2歳と始まって、なぜか最後は海賊になっちゃう人間の一生が書かれた絵巻があるんですけれども、まさにそれを僕は“同い歳”と言っています。時間軸を縦軸に割った一枚のレイヤーなんです。現実社会の時間軸の中でみると、これは年齢の差があるんですけれども、この絵巻のレイヤーの中ではみんな同い歳なんです。だから、今僕の本を読んでわからない読者がいても、その読者も同い歳なんです。よく、後でそのことに気づく人っていませんか?
たとえば、ちょっと喧嘩して、2年経ったあとに「結局、おまえの言っていることがよくわかったよ。マジで、すまんな」と言われて、「いやいや、わかったんだったらいいよ」というやりとり(笑)。だから僕は「古典を読め」と言っているんです。中国の絵巻は、西洋の遠近法なんかよりも最初から四次元世界を見せているという点で、ものすごく潔い行為なんですけれども、こうした四次元世界のイリュージョンをそのまま現実社会の中に押さえこんでいくと、実は、ポーンとメッセージが押し出されてくるんです。僕は、現実社会そのものがイリュージョン世界だと認識していますから、イリュージョンとイリュージョンがぶつかったとき、一体なにが起きると思いますか? 可能性の手前の可能性が見えているんですよ(笑)。一体どうなるか、わかりますか?
―― もしかして、現実社会が消える……んでしょうか。
坂口:そうなんです。それが僕の言う本当の「レボリューション《Revolution》」なんですね。これが「社会を変える」という行為であり、振舞なんです。現実社会から“あの街”につづく一本道、すなわちそれは、『オズの魔法使い』のドロシーが歩く“イエローブリックロード”です。僕はもうすでにあの道を歩き始めています。そして、僕は迷わず“あの街”にたどり着けるでしょう。

―― なぜ、そう感じられるのですか?
坂口:それは、あの道が人工だからです。人がつくっているからです。僕はそれを多摩川で体験しました。ロビンソンクルーソーがつくった砂利道は歩きやすいんです。文明は人がつくっているんです。人が導いてくれるんです。つまり、“あの街”はすでに現実社会の中にあるんです。ただ、僕たちが認識していないだけなんだ。だからこそ、現実をしっかり見なくちゃいけない。現実を目で見て、手で触れて、己が動いて、そして千年の熟考をすることでしか、「レボリューション《Revolution》」は起こせない。
もう一度、この本を手に取って見てくれますか?
表紙にあるこの色は何ですか?
そして、この形はなんでしょう?
黄色いレンガですね。お気づきの通り、僕はこの本にすべてのメッセージを託しています。この本を読み終えたとき、あなたの目の前には“あの街”に通ずる一本道が見えているはずです。この本には、《Practice for a Revolution》について書かれています。奇跡へのお膳立ては整いました。さて、これからが本当のILLUSION(イリュージョン)のはじまりです。
―― なんだか、壮大なマジックをみた気分で、狐につままれた気持ちです。が、ただなんと言いますか、これはもう、この本を読んでいらっしゃらない方は、もう読むしかありませんね。これからの坂口さんのご活躍がますます楽しみです。本日はお忙しい中、お時間をいただきありがとうございました。道に迷わないように気をつけて帰ります。
(取材・文:M.トワコ)
 著者プロフィール坂口恭平(さかぐちきょうへい)
著者プロフィール坂口恭平(さかぐちきょうへい)
1978年に熊本県で生まれる。早稲田大学理工学部建築学科に在学中に路上生活者の家を調査した記録を卒業論文として提出し卒業。その後、さまざまなアルバイトをしながら、卒業論文をもとにした写真集『0円ハウス』(リトルモア)を2004年に出版。その本を片手に自身の足で海外営業に出かけ、カナダ バンクーバー州立美術館で個展が決定。そこで展示した絵が初めて売れる。その後、海外に出向いてパフォーマンスを開始。現在は、東日本大震災を機に、東京生活から故郷の熊本を拠点に新政府を樹立し、初代内閣総理大臣に就任。芸術活動として、私たちに「生きるとは何か」を問い続けている。Twitter:@zhtsss
- ※1 今和次郎
- 建築学者、風俗学者。1888年に青森県弘前市で生まれ、東京美術学校を卒業。早稲田大学理工学部建築学科の教壇にたち、民家建築の研究を行う。1916年頃から民俗学者・柳田国男に師事し、柳田国男がもっとも恐れた男であると言われている。1923年関東大震災後、「バラック装飾社」を立ち上げ、バラックにペンキを用いて表現をする芸術活動を行う。と同時に都市化していく東京の街の様子や人々の暮らしを採取していく現代風俗を提唱。新しい学問領域である服装学、生活学、路上観察学なども開拓していった。1973年に没。
- ※2 ロビンソンクルーソー
- 多摩川の河川敷に長年暮らす路上生活者。坂口恭平さんが多摩川で実際に路上生活を約一ヵ月かけて体験する中で、生きるとは何か、住まうとは何か、人間とは何かという根源的な問いをご自身の生活の中で問い続けてくれた坂口さんの師匠のひとり。
- ※3 ディオゲネス
- 古代ギリシャの哲学者。前400年-前325年頃。アンティステネスの弟子で、ソクラテスの孫弟子に当たるキュニコス学派のひとり。本文に記述される内容は、大樽を住まいとする質素なディオゲネスに、羨望していたアレキサンドロス大王が直接ディオゲネスに会いにいった時のエピソード。大王が日光浴中のディオゲネスに「何か欲しいものはないか」と聞いたときにディオゲネスが言ったとされる台詞である。
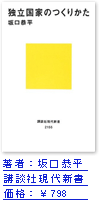 新刊『独立国家のつくりかた』(講談社現代新書)で、作家として国内の各メディアから注目される一方、海外ではパフォーマンスアートとして芸術活動を行う坂口恭平さん。しかも、彼から発せられる自身の肩書きは「建てない建築家」や「新政府初代内閣総理大臣」という奇想天外なものばかり。だが、彼の最新刊の中身は、意外にも実直に思考しつづけた一人の青年の“大人物語”であった。一体、彼は何を見て、何を感じて、何を考え、何をおこすのか。ご本人に直撃インタビューをした。
新刊『独立国家のつくりかた』(講談社現代新書)で、作家として国内の各メディアから注目される一方、海外ではパフォーマンスアートとして芸術活動を行う坂口恭平さん。しかも、彼から発せられる自身の肩書きは「建てない建築家」や「新政府初代内閣総理大臣」という奇想天外なものばかり。だが、彼の最新刊の中身は、意外にも実直に思考しつづけた一人の青年の“大人物語”であった。一体、彼は何を見て、何を感じて、何を考え、何をおこすのか。ご本人に直撃インタビューをした。





 著者プロフィール坂口恭平(さかぐちきょうへい)
著者プロフィール坂口恭平(さかぐちきょうへい)











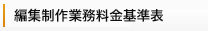



 そこで、僕はもう一度、その子から携帯を取り戻してアオに返します。またアオちゃんは携帯に夢中になります。ある程度、その子に見せつけながら。水位はグングン上がっていきます。アオちゃんは、まだいじっています。水は溜まります。すると、今度はアオちゃんのお隣りで談笑が始まります。アオちゃんの耳にも楽しそうな声が聴こえていきます。アオちゃんはまだ携帯をいじっています。僕の脳内映像では、コップの水があふれ、床にこぼれ落ちています。そこで、僕が動きます。僕は、あふれた水の受け止めるために別のコップを手にします。そして、そのコップであふれた水を受け止めます。このあふれた水を受けとめる行為を、僕は、社会実現と呼んでいます。そして、これを“親子”といいます。つまり、自己実現と社会実現は同時に行っていかなければならない。人と人が協力しないと、大人になれません。そして、心が満たされなければ、社会に向かえないんです。
そこで、僕はもう一度、その子から携帯を取り戻してアオに返します。またアオちゃんは携帯に夢中になります。ある程度、その子に見せつけながら。水位はグングン上がっていきます。アオちゃんは、まだいじっています。水は溜まります。すると、今度はアオちゃんのお隣りで談笑が始まります。アオちゃんの耳にも楽しそうな声が聴こえていきます。アオちゃんはまだ携帯をいじっています。僕の脳内映像では、コップの水があふれ、床にこぼれ落ちています。そこで、僕が動きます。僕は、あふれた水の受け止めるために別のコップを手にします。そして、そのコップであふれた水を受け止めます。このあふれた水を受けとめる行為を、僕は、社会実現と呼んでいます。そして、これを“親子”といいます。つまり、自己実現と社会実現は同時に行っていかなければならない。人と人が協力しないと、大人になれません。そして、心が満たされなければ、社会に向かえないんです。