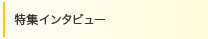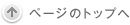|
有限会社タイプフェイス 代表 渡邊民人 TAMIHITO WATANABE 出版社に就職したのち、グラフィックデザイナーに転向。現在、多数の書籍、雑誌の装丁およびデザインを手がける。 |
今年2010年は折しも「電子書籍元年」と呼ばれ、今後、書籍のデジタル化はますます進んでいくことが見込まれます。出版のあり方が激変するであろう近い将来に向けて、編集者に求められるものとは何なのか?
グラフィックデザイナーという立場で編集の現場に関わる、(有)タイプフェイス代表の渡邊民人氏にお話を伺いました。
グラフィックデザイナーという立場で編集の現場に関わる、(有)タイプフェイス代表の渡邊民人氏にお話を伺いました。

編集者の一番そばで「編集」という仕事に関わっておられる渡邊さんの立場から見て、初めに、編集者とはどのような存在だと思いますか?
編集者というのは、言ってみればHUBのような役割だと思います。一冊の本を作ろうというとき、編集という行程の中で編集者がいろんな人をまとめ上げていくわけで、この人がいないと僕らはどうにも力を発揮しようがないんですね。著者がいないと本はできませんが、同じように、HUBになってくれる人、すなわち編集者がいなければやはり本はできない。
もっと言うと、読者がいないのに本なんか出しても意味がないということになりますよね。ということは、「読者」を見つけ出すのが編集者なわけで、結局「読者」がいるところに我々を連れていってくれるのは編集者しかいない。だから、出版においては「編集者だけしか未来を創れない」というのが僕の信じているところなんです。
もっと言うと、読者がいないのに本なんか出しても意味がないということになりますよね。ということは、「読者」を見つけ出すのが編集者なわけで、結局「読者」がいるところに我々を連れていってくれるのは編集者しかいない。だから、出版においては「編集者だけしか未来を創れない」というのが僕の信じているところなんです。
書籍のデジタル化が急速に進行していく現在、編集者が出版の未来を創っていくためには、今までとは違った意識が求められそうですね。
いえ、基本は変わらないと思います。編集者がしてることっていうのは、言わば「壮大なおせっかい」だと思うんですよ。こんな面白い知見を持った人がいるとか、こんな面白い出来事があったとか、自分が見つけたことをわざわざ周りに教えていく。それが編集者の基本なのであり、それは変わらないと思います。だけど産業が成熟していく間に、ひとつの「編集者」という型ができてしまって、なんとなく編集の本質みたいなものが宙ぶらりんになってきつつあるのかな、という気はしますね。それでも大手出版社はまだ、編集のマナーも含めて、伝統をきちんと後輩に伝えるある程度の仕組みみたいなものができているようですが、最も忙しいであろう中堅・中小の出版社では、上に立つ人も配置がコロコロ変わったりして、その辺のマナーが引き継がれにくい。そういったことで編集者の質の低下というか、編集魂みたいなものを受け継がれずに独学で来ている人が多く目につきます。
マナーとおっしゃるのは、編集の哲学や魂といったことも含めてのことでしょうか? それとも単に礼儀の問題ですか?
ソウルやスピリットということもあるんですけど、単に仕事上のマナーができていないということもあります。具体的に言うと、例えば初めての仕事の依頼でメールしか送ってこない人がいる。自分が送ったメールは当然相手も読むはず、というスタンスでメールしてくる人がいますが、それはメディアのリテラシーが低いということですよね。それがコミュニケーションツールとしての出版を企てている人がとるべき態度なのかなというのは、すごく疑問に思います。自分の条件とかスタイルに合わせろという態度が最初から見えていると、こちらとしてはモノづくりをするパートナーとしてのモチベーションがその時点で下がっちゃう。結局人を動かすのは人なので、もし自分が伝えたいものが真ん中にあって、それをいろんな人の力を借りて世の中に出していくのであれば、その一人ひとりが気持ちよく働ける場を整備するというのが編集者の役割ですから。とにかく想像力が足りない人が増えているなというふうには感じます。
では一方の、編集者としてのソウルやスピリットということに関してはいかがでしょうか。
サラリーマン編集者みたいな人が多くなってきて、ただ物事を右から左に動かすだけの人が増えてきてますね。編集者がクライアントから言われたことをただ伝えてくるだけということがある。だったら編集者はいらないですよね。クライアントと僕だけで作った方が早い。それは、自分がHUBになってる意識がないということでしょうね。そこの意識から変えていかないと、うまくいかないんじゃないかと思います。
ただ、クライアントに言われるとどうしても呑まざるを得ないという状況もあると思うのですが、そんなときに編集者はどうすべきだと思いますか?
どうしてもバイアスがかかってデザインを変えなきゃいけないといった場合、その悔しさも伝えてほしいんですよ。僕だって子供じゃないですから、どうしても変えなきゃいけないことに頑としてノーとは言えない。でも、だからこそ、本当に私は悔しいんだと、今回はどうしてもこの形で出させてほしいけど、次またやるときにはあの人のことぎゃふんと言わせましょうとか、そういう剥き出しの感情みたいなものを伝えてほしいんです。それがなければ、一緒にパートナーとしてやっている喜びがなくなっちゃう。エディトリアルの良いところって一緒にモノづくりをしている実感がリアルにあるというところです。
渡邊さんにとって、いろんな人と関わってその中でひとつのモノを作っていくという仕事のしかたはどういった意味を持つのでしょうか?
そこが僕がエディトリアルを続けている唯一のモチベーションなんですね。編集の場で言えば、打ち合わせのときに「この本って本当に楽しいんだよ」とか「こんな面白いことがあるんだよね」というふうに愛をもって語る人とやってるとすごく楽しいんですよ、こちらも巻き込まれる感じがあって。「だったらこんな感じとか良いかもしれませんね」と、こちらのアイデアもどんどん出てくる。そういうケミストリーがある瞬間が楽しくて続けているんです。結局ひとりでアイデアを練って出すときも、導火線としてのそういう打ち合わせがあればこそだったりするんですよね。たとえば自分が提案したデザインに対してNGが出る場合もあるわけで、編集者の方から「違う見せ方はできないだろうか」と言われると、最初はイヤだと思うんですけど、やってみるとすごく良かったりするときがあるんです。そんなときは本当に、例えようのないくらい良い気持ちになる。そういう瞬間が、一番のエディトリアルの楽しさが感じられる時なんですよ。だからコツコツやるのもいいけど、やっぱり人と人がぶつかったときのケミストリーが生まれるのが楽しい。そういう人と一緒に仕事をしていきたいですね。
違う人と話したりぶつかったりすることで何かが生まれてくる瞬間の喜びを感じるというのは、自分の仕事にプライドを持ちつつも、一人だけの力はたかが知れてるんだ、というスタンスでいないとできないと思います。若いうちはなかなか理解するのは難しいのでしょうが、そういうスタンスに辿り着けていない人が多すぎる気がしますね。
そうですね。自分が周りの力を引き出せていないのに、うまくいかないのを周りのせいにして、それで結果、総和としての力が一個人以下に陥ることだってたくさんあると思うんですよ。その意味でやっぱり編集者ってHUBなので、プラスもマイナスもすべてその彼、彼女が担っている。たとえば100の力を持った人材を4人集めたら400になるはずなのに、それが100の4乗になるのかゼロになるのか、あるいはマイナスにしてしまうのか、っていうのは編集者次第。だから編集者がとにかく未来を作っていくべき存在であるというのは間違いないですよね。企画然り、著者発掘然り、チームのコーディネート然り、その辺の総和がすべて出てきちゃう。だからやっぱり編集者っていうのは、何よりもHUBであるという自覚を持っていてほしいなって思うんですよ。
1 l 2