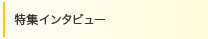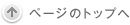|
ゲーム作家・新しい編集者。1964年生まれ。『ぷよぷよ』『トレジャーハンターG』『BAROQUE』『魔導物語』など多くのゲームの企画・監督・脚本を手がける一方でライターとしても活躍中。立命館大学映像学部教授、宣伝会議「編集・ライター養成講座上級コース」専任講師。著書に『仕事を100倍楽しくするプロジェクト攻略本』( KKベストセラーズ)、『デジタルの夢でメシを食うためにボクらは! 』(マイクロマガジン社)、『自分だけにしか思いつかないアイデアを見つける方法』(日本経済新聞出版社)、共著に『日本文学ふいんき語り』(双葉社)、『誰でも作れる電子書籍』(インプレスジャパン)などがある。ブログ:こどものもうそうblog |
ゲームクリエイターとして『ぷよぷよ』『トレジャーハンターG』などの名作を生み出し、近年は大学教授、ビジネス書の著者、ポータルサイトのライターと、いちゲームクリエイターの範疇にはとうてい収まりきらない活躍をみせる米光一成氏。さらに米光氏は電子書籍ならぬ「電書」制作の活動にも意欲をみせ、「新しい編集者」という肩書きを加えている。作者と編集者、読者の境目がなくなると言われる時代。米光氏の言う「新しい編集者」について聞く。

ゲーム作家、講師、ライター、そして最近では「新しい編集者」という肩書きでもお仕事をされていらっしゃいますが、米光さんがイメージされる「新しい編集者」とはどのような編集者なのですか?
僕はiPadやツイッター、フェイスブックの登場で、これからは「編集」の定義が変化していき、仕事も拡大していくと思っているんです。それで従来の出版ビジネスにおける「編集者」との違いを分かってもらうために、「新しい編集者」と名乗っています。 編集が変わっていく理由の一つに、iPadやKindleの登場がありますが、それは1983年頃のゲーム業界の状況によく似ています。ゲーム業界の1983年というのはファミコンが発売になった年で、そこからゲーム業界が生まれたと言ってもいいくらいです。 それまでゲームはプログラマーとイラストレーターでつくっていました。でも、ファミコンブームで仕事が膨大に増えて、ゲーム制作でハブになれる人が必要になった。その頃です、ゲームデザイナーという職業が生まれたのが。僕は当時勤めていた会社のなかで「ゲームデザイナー」という肩書きで仕事をした第1号でした。 今までのルーチンワークとは違う仕事が生まれるときは、新しい働き方、新しい職種が生まれるんです。だから違いを分かってもらうためにあえて「新しい編集者」と自分から名乗っています。僕の「新しい編集者」という肩書きは、従来の「出版」という枠での編集者とは競合しません。 分かりやすくいえば、ソーシャルメディアを使って人を集めて編む、場づくりをする。そしてそこで「電書」を媒介にしてコミュニケーションをとるという試みをしているので「新しい」と言ったほうが、伝わりやすいかと思うんですよね。

米光さんがあえて「電書」と呼ばれているものと、従来の「電子書籍」の違いを教えてください。
僕が「電書」と言っているものは、書籍を単に電子化したものではなく、違うメディアです。ページ数も1ページでもいいし5千ページでもいい。ページという概念がなくてもいい。いつ出してもいいし、いつでも書き換えられる。書籍ではないんですね。 僕が講師を務める宣伝会議の編集講座の受講生と、2010年に「電書部」を結成して、その成果発表の場として「電書フリマ」を開催しました。デジタルな電書をリアルな対面で販売するという試みです。 やり方は会場にパソコンを持ち込んでネットワークにつなげておくんです。そこにお客さんが来て、サンプルを見てもらう。お客さんは欲しくなったら、販売員である作者と値段を交渉して、お金を払い、メールアドレスを伝える。そして電書がメールで届くという仕組みです。値段は大体100円くらいでした。 渋谷と吉祥寺と京都のカフェなどで同時開催したんですが、販売した電書は64種類。777人の集客があって、購入数は5209冊でした。老若男女が集まって、電書をきっかけに会話が深まっていくのが面白かったです。 同じ関心事を持っている人同士が電書をハブに出会い、コミュニケーションをとる。その後、フリマで話したことや読者とのやり取りがヒントになって、作者は電書を書き換えたり、次の電書をつくったりということを実際にやりました。 今、書店で同じ書籍を買った人たちは作者を巻き込んでコミュニケーションをすることは難しい。だけど、電書ならば作者と読者でコミュニケーションをすることが可能だし、そこから元とは違った本が生まれたりするでしょう。電書をハブにしてコミュニケーションや作品が進化していく。それが電書フリマをやってみて、実証されたのではないかと思います。
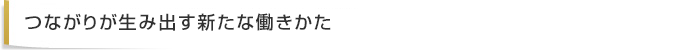
同人誌から出発したカルチャー誌の黎明期に似ていますね。
そうなんです。たとえば、僕の知人にインコのマニアがいて「インコ電書」をつくった人がいます。確かに紙の雑誌で「月刊インコ」は企画としても難しいし、採算は見込めないです。でも電書ならば気軽にできて、今やインコマニアのコミュニケーションのハブになっているんです。その人は勤めていた会社を辞めてしまい、今、「インコ編集長」と名乗っています。 彼を見ていて感じたのは、ビジネスとして儲けるというよりはコミュニティをつくって、その人たちに喜んでもらえることに価値を置いています。「儲からなくてもいい」と覚悟できるのも、人とのつながりを重視する今の時代だからこそです。 ソーシャルな時代では「編集者」というのは職業ではなくて、属性、タグみたいなものになっていくのではないか。自分の一番専門的なことが職業になって、人とのつながりが財産になっていくのではないかと、僕は予感しているんです。
なるほど。本をつくる、というよりもコミュニティのハブとしての編集者なんですね。
電書はワークショップとかオフ会とか、同じ趣味の人が集まるイベントの媒体に一番適していると思いますね。 たとえば映画のトークイベントなら、イベントが終わったと同時にその対談をまとめて参加者に送信することができます。イベントに参加しているから空気感も伝わるし、即時性が大事だから、多少テキストが荒削りでも許されます。今はそういったイベントを開催するにも、ソーシャルメディアで告知すれば宣伝費もかからないですしね。
ネットだと不特定多数の人が見るので炎上する可能性があるけど、電書なら顔の見える人に届けられます。コミュニケーションの可能性が広がっていくと思うんです。